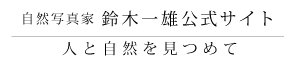私は、風景写真愛好家との付き合いが多い。だがそれらの方々は、ほとんどが高齢者だ。それゆえに、永遠にお別れする事態が毎年のように生じる。そして時折、関係が深かった方々のご遺族から、残された作品の扱いについて相談を受けることがある。それについて、今でも忘れがたいふたつの事例がある。
ひとつは、私のフォト寺子屋「一の会」の会員だったKさんである。85歳で亡くなられたKさんは、寿命を全うして他界された。半世紀以上にわたって撮り続けてきた作品数は膨大であったが、残念ながら、私が提唱してきた「自分史」の原稿は残されていなかった。アメリカに在住されているお孫さん(彼女は、一年前の尾瀬撮影会にKさんのお供をされた)も駆けつけ、一週間がかりでポジ作品を整理された。
その後に奥様から、本人が歓ぶことを何かしてあげたいがどうしたらよいか、という相談をもちかけられた。私は、ご家族のみなさんの寄せ書きや家族写真なども入れた作品集を作り、一周忌の引き出物にされてはどうか、と勧めた。奥様も賛同され、各自の原稿に取り組んでくれた。私は板見浩史さんの協力を得て、二人がかりで作品の選定と製作に取り組んだ。やがてできあがった作品集は、Kさんの一周忌法要の引き出物となった。身内からも参列者からも、故人を偲ぶ大切なものとして本当に歓ばれたようである。
二つ目の事例は、二十年以上もお付き合いが続いたTさんの話である。過去に写真展を開催されたこともあるベテランのTさんは、新たなるテーマの集大成と発表に向けて熱心に取り組んでいた。だが、病魔によって志半ばでこの世を去ってしまった。奥様が遺品を紐解いていると、まとめられた作品と写真展を開催するための資金、そして私の手紙(次なる発表について作品選定をお願いしたいというTさんから依頼に対し、了解しましたという私の返事)がひとつの箱に大切に保管されて出てきたという。奥様から、追悼の写真展をやってあげたいが面倒を見て頂けないか、と相談された。私は、「喜んでお手伝いします。ただ、写真展もいいですが、故人を偲ぶ作品集を一周忌の引き出物にするのもいいですよ」と返事した。それでは検討しますということだったが、なかなか返事はこなかった。
やがて一年ほど過ぎた頃に、その奥様から電話がかかってきた。消え入りそうな声で話された内容に、私は愕然とした。それは、息子さん夫妻(特にお嫁さんの意見で)から財産分与の裁判を起こされ、Tさんが残していた写真展資金も使えなくなってしまった、というのであった。私は慰める言葉もなく、もし事態が進展して何かお手伝いすることができたらいつでも申しつけて欲しい旨のことを話し、電話をきった。だが、その後の連絡は途絶えたままである。
高齢者が取り組む風景写真においては、一般的な趣味の範疇を超え、生き甲斐として、命をかけて真剣に取り組む人がかなりいる。だが、他界された後の作品の行方とそれを天から見届ける本人の想いの行方は、さまざまである。