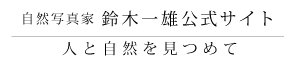私が、
初めて“白い虹”に出会ったのは、
尾瀬ヶ原であった。
そのときは、
まるで湿原の精霊を見たような感覚を覚えた。
尾瀬は、その後も私に、
白い虹に何度も出会う機会を与えてくれた。
七色の虹に出会ったとき、
私は、四葉のクローバーを見つけたようなしあわせな気分になる。
そして、
白い虹に出会ったときは、
何故か、
祈りを捧げたい気持ちが湧いてくる…。
The first time I saw a white rainbow.
It was in Ozegahara.
At that time,I felt as if I had seen the spirit of the marsh.
After that, Oze gave me many opportunities to see the white rainbow.
When I come across a rainbow of seven colors, I feel as happy as if I had found a four-leaf clover.
And when I came acrss a white rainbow, for some reason, I feel the urge to pray….