
ある夜
何度も訪れている 遠方の梅たちから
お呼びがかかった
明日の朝に来れますか という
私は 急いで準備をすませ
車を走らせた
早朝に たどり着くと
大地は雪で覆われ
真っ白な世界に 変貌していた
濃い朝霧が 梅林に 結界を張った
私は 一人
その中にいることを 許された
やがて 古木の梅が 梅の精霊が
舞い始めた
静かに ゆったりと
舞い始めた
(静岡県伊豆市)
≪作画の鍵≫
□聲をきく
□描くように
□心を込めて
One night,
I was approached by a distant plum grove
that I have visited many times.
They asked if you could come by tomorrow morning.
I hurriedly made my preparations
and drove off.
When I arrived in the early morning,
the land was covered with snow
and had turned into a white world.
The thick morning fog had put a boundary around the plum grove.
I was the only one allowed to be in it.
Soon, the old plum trees,
the spirits of the plum trees began to dance.
Quietly, slowly, they began to dance.
(Izu City, Shizuoka Prefecture)
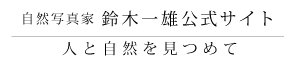





、「夜明けの一閃(いっせん)」-コピー_1_R-470x343.jpg)


