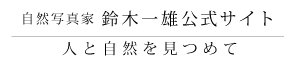2018年3月13日、ネットニュースを見ていた私は衝撃を受けた。何と、およそ100年ぶりに自生種の桜の新種が発見され、“クマノザクラ”と命名されたという。桜をこよなく愛する私には、本当に驚きだった。何しろ、園芸種の桜はおよそ600種類あるのに対して,日本の自生種の桜はわずかに9種類(沖縄のカンヒザクラを自生種と認める学説では10種類)しか存在していない。“クマノザクラ”は、熊野川流域を中心として広く分布しているらしい。これまでヤマザクラと思われていたものが、今回の詳しい調査の結果、あらためて新種と判明したという。
原稿執筆などの立て込んでいた仕事を終えて、私がようやく東京を出発できたのが22日の夜だった。翌朝、私は、和歌山県古座川町にあるクマノザクラの標本木(認定されただひとつの個体)の桜を、胸を熱くしながら見つめていた。かなり散ってはいたが、花色や葉の形などのクマノザクラの特徴をひとつずつじっくり確認することができた。
そのあと、三重県熊野市の丸山千枚田へと急いだ。標高の高いあの地域ならば、クマノザクラはほぼ満開と予測したからだ。期待通り桜は見事に咲き誇っていたが、意外なことに誰一人いなかった。世紀の大発見というのにどうしたことか、不思議だった。おかげで私は、クマノザクラかヤマザクラかの識別を行いながら(地元の人も、まだどれがクマノザクラか断定できないため)、二日間にわたって心ゆくまでシャッターをきることができた。
そのときの作品数点は、翌年2019年に写真展「サクラニシス」、写真集「サクラニイキル」で発表した全国の桜作品の中に収録した。そして、特に気に入ったこのクマノザクラ作品は、写真展DМの写真として使用した。昨年に立ち寄った時、熊野市が作成した“クマノザクラめぐりマップ”の中で、私がDМに使用した桜が“紀和町のクマノザクラのシンボルツリー”と紹介されているのを知った。私は、嬉しかった。
(三重県熊野市)
≪作画の鍵≫
□新発見の感動
□櫻の“気”を描く
□全身全霊
On March 13, 2018, I was watching the online news and was shocked. For the first time in about 100 years, a new species of native cherry tree has been discovered and named the “Kumano cherry”. As a great admirer of cherry blossoms, I was really surprised. While there are about 600 horticultural species of cherry trees, there are only nine species of native cherry trees in Japan (10 according to the theory that recognizes Taiwan cherry in Okinawa as a native species). “Kumano cherry” is said to be widely distributed mainly in the Kumano River basin. The cherry tree, which had been thought to be a conventional mountain cherry, was found to be a new species as a result of the detailed research.
I was finally able to leave Tokyo on the night of the 22nd, after finishing the manuscript and other busy work. The next morning, I was looking at a specimen tree of the Kumano cherry tree (the only one certified as such) in the town of Kozagawa, Wakayama Prefecture, with a burning desire in my heart. Although it was quite scattered, I was able to carefully check the characteristics of the Kumano cherry, such as flower color and leaf shape, one by one.
After that, I hurried to the rice terraces in the Maruyama district. in Kumano City, Mie Prefecture. I predicted that the Kumano cherry trees would be in full bloom in that high altitude area. As expected, the cherry blossoms were in full bloom, but surprisingly, no one was there. I wondered what had happened to this great discovery of the century. Thanks to this, I was able to take pictures to my heart’s content for two days while trying to identify the Kumano cherry or wild cherry trees (At that time, even the locals couldn’t determine which one was the Kumano cherry).
I included some of my work from that time in the following year, 2019, in the photography exhibition “Sakuranisys” and the photo book “Sakuraniikiru”. And the kumano cherry works that I particularly liked were used as photos for the exhibition DМ. When I dropped by last year, I found out that the cherry tree I used for the DМ was introduced as “the symbolic tree of the Kumano cherry in Kiwa Town” in the ” Kumano cherry Tour Map” prepared by the city. I was so happy.
(Kumano City, Mie Prefecture)